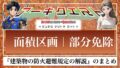竪穴区画において、任意の耐火構造等の建築物の取り扱いを教えて下さい!

解釈と条件について、『建築物の防火避難規定の解説』をもとに解説します!
はじめに

建築設計において、防火・避難に関する規定は、建物の安全性を確保する上で極めて重要な要素です。中でも「竪穴区画」は、火災時の煙や火炎の垂直方向への延焼を防ぐための基本的な仕組みとして位置づけられています。
本記事では、建築基準法により耐火建築物とする義務がない建物であっても、自主的に主要構造部を耐火構造や準耐火構造とした場合における竪穴区画の取り扱いについて、国土交通省が監修する『建築物の防火避難規定の解説』をもとに詳しく解説いたします。

第1章 自主的に主要構造部を耐火構造等とした竪穴区画について

建築基準法第27条および第61条等により耐火建築物とする法的な義務がない建築物であっても、主要構造部を耐火構造とした建築物又は、建築基準法施行令第136条の2第1号ロに掲げる建築物(延焼防止建築物)とした場合には、竪穴を区画する必要があります。(下図イメージ)

(耐火建築物等としなければならない特殊建築物)
第二十七条 次の各号のいずれかに該当する特殊建築物は、その特定主要構造部を当該特殊建築物に存する者の全てが当該特殊建築物から地上までの避難を終了するまでの間通常の火災による建築物の倒壊及び延焼を防止するために特定主要構造部に必要とされる性能に関して政令で定める技術的基準に適合するもので、国土交通大臣が定めた構造方法を用いるもの又は国土交通大臣の認定を受けたものとし、かつ、その外壁の開口部であつて建築物の他の部分から当該開口部へ延焼するおそれがあるものとして政令で定めるものに、防火戸その他の政令で定める防火設備(その構造が遮炎性能に関して政令で定める技術的基準に適合するもので、国土交通大臣が定めた構造方法を用いるもの又は国土交通大臣の認定を受けたものに限る。)を設けなければならない。
一 別表第一(ろ)欄に掲げる階を同表(い)欄(一)項から(四)項までに掲げる用途に供するもの(階数が三で延べ面積が二百平方メートル未満のもの(同表(ろ)欄に掲げる階を同表(い)欄(二)項に掲げる用途で政令で定めるものに供するものにあつては、政令で定める技術的基準に従つて警報設備を設けたものに限る。)を除く。)
二 別表第一(い)欄(一)項から(四)項までに掲げる用途に供するもので、その用途に供する部分(同表(一)項の場合にあつては客席、同表(二)項及び(四)項の場合にあつては二階の部分に限り、かつ、病院及び診療所についてはその部分に患者の収容施設がある場合に限る。)の床面積の合計が同表(は)欄の当該各項に該当するもの
三 別表第一(い)欄(四)項に掲げる用途に供するもので、その用途に供する部分の床面積の合計が三千平方メートル以上のもの
四 劇場、映画館又は演芸場の用途に供するもので、主階が一階にないもの(階数が三以下で延べ面積が二百平方メートル未満のものを除く。)
2 次の各号のいずれかに該当する特殊建築物は、耐火建築物としなければならない。
一 別表第一(い)欄(五)項に掲げる用途に供するもので、その用途に供する三階以上の部分の床面積の合計が同表(は)欄(五)項に該当するもの
二 別表第一(ろ)欄(六)項に掲げる階を同表(い)欄(六)項に掲げる用途に供するもの
3 次の各号のいずれかに該当する特殊建築物は、耐火建築物又は準耐火建築物(別表第一(い)欄(六)項に掲げる用途に供するものにあつては、第二条第九号の三ロに該当する準耐火建築物のうち政令で定めるものを除く。)としなければならない。
一 別表第一(い)欄(五)項又は(六)項に掲げる用途に供するもので、その用途に供する部分の床面積の合計が同表(に)欄の当該各項に該当するもの
二 別表第二(と)項第四号に規定する危険物(安全上及び防火上支障がないものとして政令で定めるものを除く。以下この号において同じ。)の貯蔵場又は処理場の用途に供するもの(貯蔵又は処理に係る危険物の数量が政令で定める限度を超えないものを除く。)
4 前三項に規定する基準の適用上一の建築物であつても別の建築物とみなすことができる部分として政令で定める部分が二以上ある建築物の当該建築物の部分は、これらの規定の適用については、それぞれ別の建築物とみなす。
(防火地域及び準防火地域内の建築物)
第六十一条 防火地域又は準防火地域内にある建築物は、その外壁の開口部で延焼のおそれのある部分に防火戸その他の政令で定める防火設備を設け、かつ、壁、柱、床その他の建築物の部分及び当該防火設備を通常の火災による周囲への延焼を防止するためにこれらに必要とされる性能に関して防火地域及び準防火地域の別並びに建築物の規模に応じて政令で定める技術的基準に適合するもので、国土交通大臣が定めた構造方法を用いるもの又は国土交通大臣の認定を受けたものとしなければならない。ただし、門又は塀で、高さ二メートル以下のもの又は準防火地域内にある建築物(木造建築物等を除く。)に附属するものについては、この限りでない。
2 前項に規定する基準の適用上一の建築物であつても別の建築物とみなすことができる部分として政令で定める部分が二以上ある建築物の当該建築物の部分は、同項の規定の適用については、それぞれ別の建築物とみなす。

また、自主的に主要構造部を準耐火構造とした建築物又は、建築基準法施行令第136条の2第2号ロに掲げる建築物(準延焼防止建築物)とした場合についても、同様の取り扱いとします。
たとえば、延べ面積が200m²を超える一戸建ての住宅であって、主要構造部を耐火構造または準耐火構造とした場合などがこれに該当します。
このように、たとえ耐火建築物または準耐火建築物とすることが求められていない建築物であっても、安全の観点からは竪穴区画を設けることが望ましいとされています。
したがって、自主的に主要構造部を、耐火構造若しくは準耐火構造とした建築物又は延焼防止建築物若しくは準延焼防止建築物の場合であっても、竪穴区画を免除しないこととします。
第2章 「勇者と魔獣で学ぶ!防火避難の解説書」を手に入れよう!


建築基準法や国土交通省の告示や通達を見ても、
本記事に関する情報は、載ってニャイよね?

その通り!『建築物の防火避難規定の解説』に載ってるよ!
でも1冊5,000円。文字も多くて読みにくいんだよね。。。

高い!!!文字ばかりっも辛いニャ。。。


残業時間を減って、お金も浮くにゃ!今夜は美味しい魚を食べるにゃ!


以下リンクより購入できます!じゃあ冒険の先で待っているね!

設計をしていると、行き詰まる瞬間が訪れます。
その理由はシンプルです。防火避難規定の多くは建築基準法や告示などでは載っておらず、お金を持っている人しかリーチできない情報格差が存在しているからです。

この閉ざされた状況を変えたくて、この記事を含め150記事以上をオープンソースにして皆様にわかりやすくして公開しています。しかし、これらが一冊にまとまっていたらいいのに。。。なんてお声に応えるべく、880ページを超える情報をまとめた一冊を作りました。
スポンサーリンクおわりに

今回ご紹介したように、「竪穴区画」は義務的な耐火建築物に限らず、自主的に耐火構造等とした建物にも原則として適用される点に注意が必要です。建築基準法だけでは読み取れない実務的な解釈や運用は、『建築物の防火避難規定の解説』に詳述されています。
スポンサーリンク